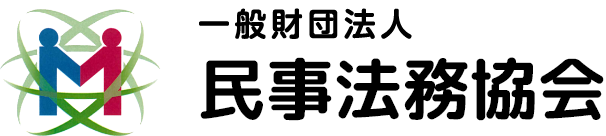


一人暮らしのSさんは、今年1月の訪問看護の診察で、胸にこぶし大のしこりが見つかり、大学病院で精密検査をしたところ、乳がんと診断され、後見人はいくつかの検査に同行し、本人と一緒に医師の説明を聞きました。Sさんとの会話は成立するものの、すぐ話をしたことを忘れるなど、記憶力は相当低下しています。Sさんの治療は、腫瘍が大きく、まず抗がん剤で小さくした後、切除するというものですが、乳がんであると説明されても、すぐに忘れてしまうため、治療の必要性をSさんは理解できていませんでした。
82歳のSさんが、厳しい化学療法に耐えられるのか、副作用によってかえって体調が悪化するのではないかと、後見人は逡巡しましたが、主治医は最も適切な治療方針と考えており、Sさんも治療を拒否するような様子がないことから、予定した治療を行うことになりました。
後見人はケアマネージャーと相談し、3週間に1回6か月間にわたる抗がん剤投与期間中、Sさんが自宅で生活するのは難しいと判断し、その間だけ、入院先に近い有料老人ホームに入居してもらい、介護スタッフに囲まれ支援できる環境に配慮しました。
抗がん剤は予想以上の効果があり、触診では分からないほど小さくなったため、4回目の投与で中止となり、切除手術はしなくてすむかもしれないと期待しましたが、まだ小さな腫瘍があったため、主治医から、手術は必要と説明され、すぐに切除手術の準備が進められました。
後見人は、腫瘍の大きさから、乳房の部分切除と思っていましたが、医師の説明で全部切除であることが分かり、Sさんがこれを知ったときのことを考えると、胸が塞がれる思いでした。
心配したとおり、手術前後、Sさんは不穏な状態になりましたが、今の状況をすぐに忘れてしまうためか、入院から約4週間の術後療養期間を経て退院し、有料老人ホ ームに戻ることができました。

Iさんは、所有する財産を全て弟のKさんに相続させるとの公正証書遺言を作成していましたが、同遺言書には、KさんがIさんより先に死亡した場合に、所有する自宅不動産について特段の定めをしていませんでした。Iさんは、自身の死後のことをきちんとしておきたいという気持ちが強く、生前に両親の墓じまいなどを行っていたものの、自身の財産については「親族間で争いになるのは望まない。」「疎遠だった親族に財産を相続させたくない。」と言っていたので、Iさんの意思を実現するために、自宅を処分して金銭に換価することにしました。
居住用不動産の処分について、家庭裁判所の許可審判を受けました。
Iさんは、施設に入居していますが、自宅に残した家財を気にかけ、「整理はしたいが、ただ捨てるのではなく有効利用してほしい。」とおっしゃっていましたので、Iさんを何度か自宅にお連れして、家財整理の支援をしました。
家庭裁判所から売却が許可されたものの、建物を解体するに当たり、家財を丸ごと解体業者が処分してしまう可能もあったため、Iさんの希望を考慮して、家財撤去業者に家財の処分を依頼しました。
自宅の売却については、敷地の測量において隣地所有者の立会い等に若干の時間を要しましたが、概ね順調に進めることができ、金銭に換価することができました。
当初、Iさんは、自宅が売却されたことに寂しさを感じられていたようでしたが、時の経過とともに、元気を取り戻されました。
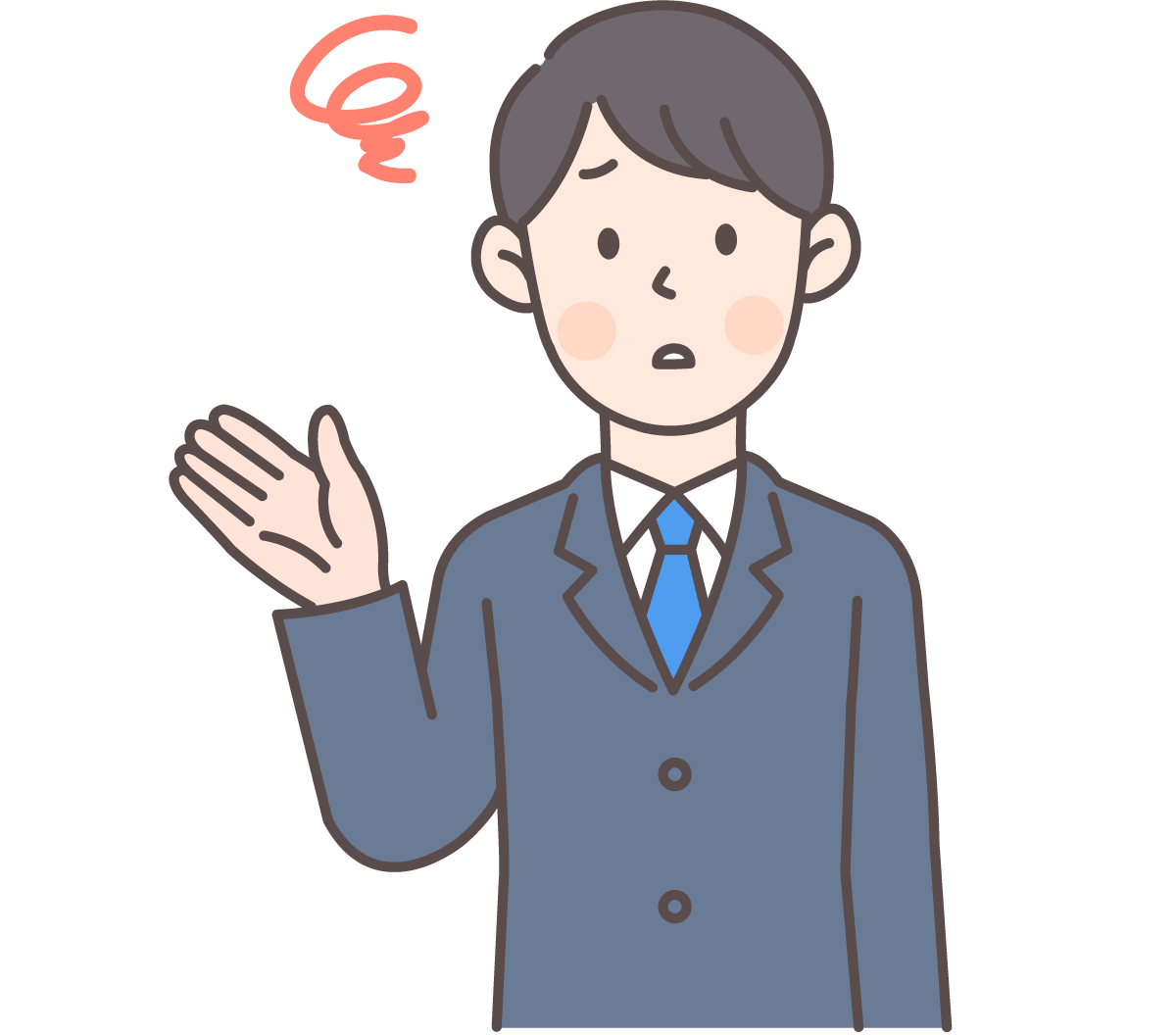
介護施設に入所していたAさんには、当初、別の後見人が選任されていました。Aさんには死亡した姉がおり、その相続が未了であったことから、後見人が関与して遺産分割協議を行った結果、遠方にある不動産をAさんが取得したため、これに不満を抱いたAさんの長男がクレームを頻繁に寄せるなどして、後見人と長男との関係が悪化し、後見業務遂行が困難となったことから、当協会が後任の後見人に就任することになりました。
唯一の親族である長男との関係修復と遠方の不動産の管理が課題でした。
長男との関係修復については、情報交換が不足し遺産分割に長男の意向が反映されなかったことが関係悪化の原因と思われたことから、可能な限り長男との情報交換を密にしたり、Aさんの訪問には長男と日程調整の上で同行するなど、信頼関係の構築に努めました。
相続した不動産の管理方針については、当該不動産を売却することになったものの、物件が遠方にあり現地の状況に不案内であったこともあり、仲介業者の選定が困難となっていた中、不動産所在地の「空き家等ネットワーク協議会」の情報を得て、当該協議会から地元の宅建業者の紹介を受けて売却を進め、何度か現地を訪れる必要はあったものの、幸いにしてスムーズに売却ができて、遺産分割の際の評価額がほぼ確保できました。後見人は、その間、長男への詳細な報告や協議に心がけました。
その後、Aさんは他界されましたが、財産引継の際、長男からお礼が述べられました。

Bさん(80代女性)は、要介護1、認知症、聴覚障害のため手話による通訳が必要でした。日常の生活において、金銭管理及び家事は、死亡した夫が全て行っていました。Bさんは全く管理ができないことから、心配した親族からの申立てにより、当協会が後見人に就任しました。
被後見人の夫は、死亡時に、全ての財産をBさんに相続させるとする自筆証書遺言書を残していたことから、後見人は、当該遺言書による相続手続を行うために、必要となる戸籍謄本等の書類を整え、裁判所へ遺言書検認申立てを行い、同裁判所において行われた遺言書の検認に立ち会いました。その後、この遺言書に基づいて、夫名義の預貯金の相続手続や夫名義のマンションの相続登記を行いました。
また、夫は生前、東北地方にある本家の墓に入りたいと希望していましたが、それまで相談を受けていた担当ケアマネージャーが交替したこともあり、納骨の話が進んでいない状況でした。
後見人は、後任のケアマネージャーに立会いを依頼し、手話通訳者同席の下で、配偶者の生前の意思を尊重して本家の墓へ納骨(Bさんも将来同じ墓に納骨)することについて、Bさんに確認したところ、希望したことから、直ちに、本家を継いでいる甥と電話連絡をとり、納骨について依頼をしました。
後見人は、お寺や親族との調整に関する進捗状況を確認するため、甥と数回にわたって連絡調整を行い、遺骨を被後見人の自宅から甥のもとに搬送しました。
その後、無事納骨が終わり、位牌が被後見人の自宅に送られてきました。
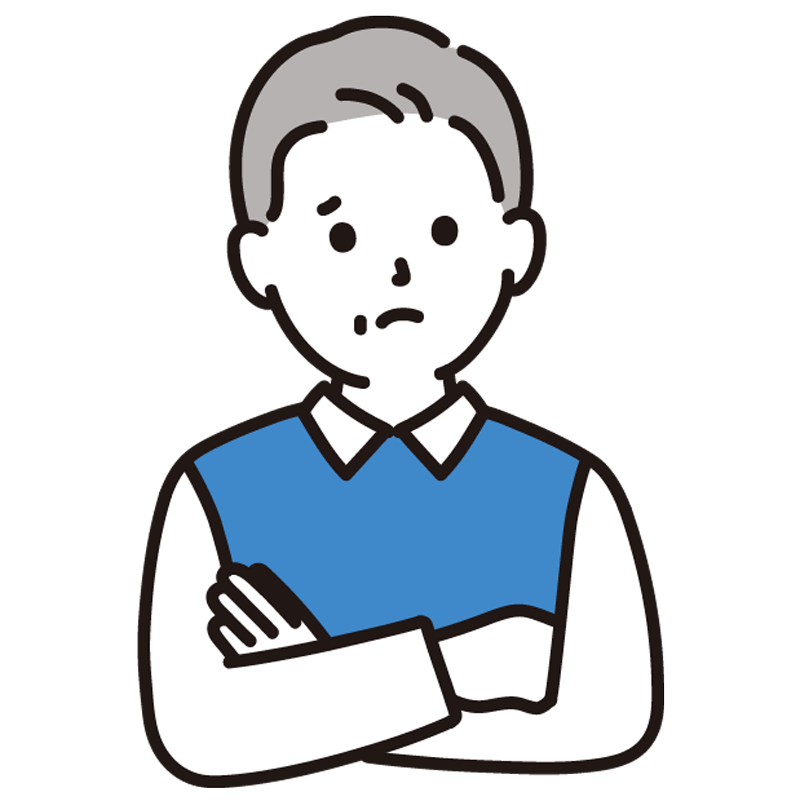
Fさんは、気ままに一人暮らしをしていましたが、家賃を滞納するようになり、生活を心配した大家さんが本人と共に自治体の窓口に相談に訪れ、その後、首長申立てにより、成年後見が開始されました。
Fさんは、金銭の管理や判断が苦手だったので、知人に通帳やカード類を預けていましたが、預けた後もクレジットカードを使用していたようです。そして、郵便物等を精査したところ、クレジット会社2社と債権回収会社2社から借入金の返済を求められていることが分かりました。
債権回収会社からは「減額和解のご提案」や「法的手続の準備に入らざるを得ません。」と題した通知が届いていました。
これらの請求書を受け取ったFさんが電話で今後の返済に関する話をしたり、一部でも弁済していた場合には、債務を承認したものとして取り扱われる可能性がありましたが、Fさんは、これらの郵便物について、内容を見ることもなく放置していたということで、返済について意思表示をしたことはなかったようでした。
そして、最終の弁済日からいずれも5年以上経過していることは、まず間違いないようでした。そこで、後見人は、Fさんの法定代理人として、4社に対し、消城時効を援用する旨の通知を内容証明郵便で送付しました。
通知の発送から1年以上が経過していますが、クレジット会社及び債権回収会社からの連絡は全くありませんので、後見人としては、Fさんの債務処理は完了したものと考えています。
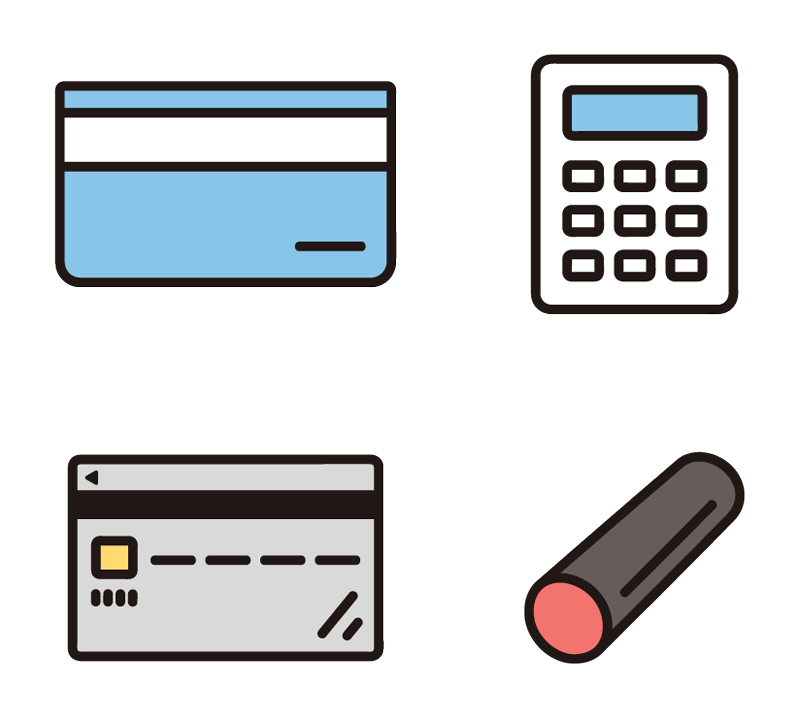
Tさんは、要介護1、アルツハイマー型認知症と診断されており、通帳や印鑑の紛失による再発行や、年金受給後1日で数十万円を使ってしまうなどの行動が増えたことから、区長申立てにより、当協会が後見人に就任しました。
Tさんの配偶者の葬儀は、近隣の支援者らによって執り行われていたものの、後見人就任時には、Tさんの財産では、葬儀費用等の支払いができず、債務としてそのまま残っていたことから、配偶者の他界に伴う相続財産を現金化して債務の支払いを急ぐ必要がありました。
後見人は、就任後直ちに相続人を確定させ、Tさんを除く相続人7名(以下「相続人7名」という。)に対して、相続財産に関する手続は、①後見人が相続人を代表して行うこと、②相続財産は法定相続分に応じて分配すること、③Tさんの自宅はTさんが相続するが、法定相続分を超えて取得する分は金銭にて分配すること等を説明するとともに、遺産分割協議書(案)を作成し、これに同意を求めました。
その結果、相続人7名から同意が得られましたので、遺産分割協議書に署名、押印を求めた後、被相続人が加入していた年金保険及び預貯金等の払戻しを受け、相続人7名への分配と未払いの葬儀費用等の支払いを済ませました。また、被相続人と共有名義となっていたTさんの自宅を単独名義とする相続登記を行いました。
Tさんの配偶者の遺骨は、現在も自宅に保管されています。
>Tさんからは、仮に自分が死亡した場合には、配偶者とともに地元の合葬墓に埋葬して欲しい旨言われているので、後見人としては、この希望をかなえたいと考えています。
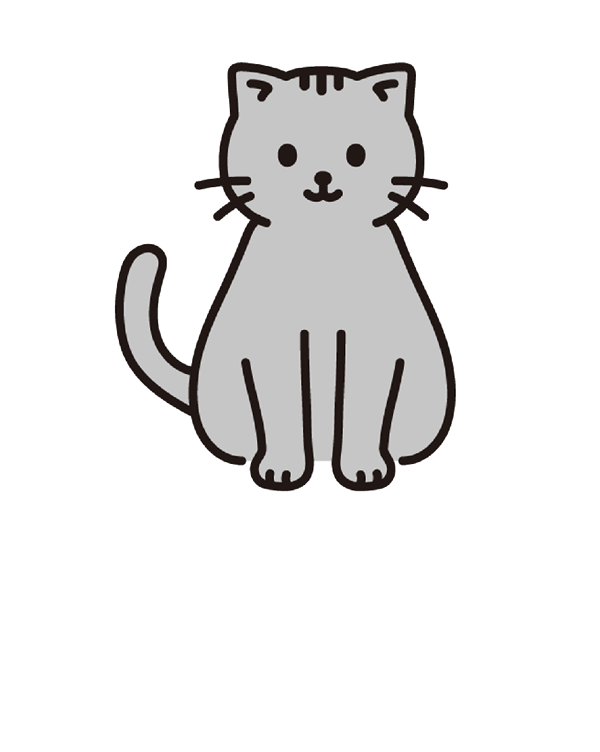
Uさんは、アルツハイマー型認知症と診断され、本人の持ち家でヘルパーの支援を受けながら、猫のタマちゃん(11歳)と暮らしていました。最近は足腰が弱り、転倒しがちになっていたところ、6月の猛暑の朝、脱水症状で救急搬送され、2週間の入院を経て、高齢者施設に入所することになりました。
問題はタマちゃんの今後の暮らしです。
Uさんには、もしもの時にはタマちゃんを引き取ってもらえそうな知人がいました。そこで、後見人は、Uさんの入院後、タマちゃんをペットホテルに泊まらせ、健康診断を受けさせました。その結果、猫エイズ陽性と判明したため、先住猫のいる知人宅では飼えないということになり、急きょ、貰い手を探しましたが、なかなか見つかるものではありません。
そのため、飼い主を失った猫を引き取り、里親を募集してくれる団体に譲渡することを検討し、保護猫団体「N会」に連絡を取ると、N会では、指定の動物病院で健康診断や治療を受けてもらい、その後、会費を支払って譲渡し、里親探しをするという対応だとのことでした。タマちゃんの場合、これまで動物病院との関わりがなかったため、当初の健康診断・治療をしっかりすると、会費を含め80万円以上の支出となり、Uさんの資力では難しいことから、他の団体を探すことにしました。
次に、隣県にある「T会」に照会すると、施設見学も可能というので早速訪問しました。T会は自然豊かな立地にあり、敷地が広く、猫舎は清掃や空調が行き届いており、手作りのキャットタワーなどの遊具が多数設置されていました。エイズキャリア用の猫舎は8畳ほどのスペースで、5匹の猫がくつろいでいました。T会によると、夏は子猫がたくさんいる時期なので、シニア猫の里親探しは非常に厳しいとのことでした。
後見人は、ここならタマちゃんもゆっくり過ごせそうだと感じましたので、T会にタマちゃんを譲渡しました。
現在、Т会のホームページを見ると、今も飼い主募集中のタマちゃんの様子を写真で見ることができますので、時折、そっと確認しています。

Wさん(被保佐人)は、総額数千万円の宝石類をカードローンで購入しましたが、分割返済が滞るのをおそれて自殺未遂を起こしたことから、家族に多額の負債があることを知られることになりました。そこで、Wさんと同居していた親族のYさんは、Wさんの財産管理の必要性から保佐開始の申立てを行い、Yさんが保佐人に就任しました。
その後、Yさんは、仕事が多忙となったことから、自分の家族にWさんの財産管理を任せるようになり、その結果、Wさんの生活費とYさん家族の生活費が一緒に処理されることになりました。
そこで、家庭裁判所は、Yさんに対し、Wさんの財産の一部がYさん家族の生活費に使用されていることや使い道が不明な支出があることを指摘するとともに、当協会を保佐人に追加選任しました。そのため、当協会は、権限分掌による財産管理を行うことになりました。
当協会が保佐人に選任された際、家庭裁判所から「Yさんが保佐人として問題なく財産管理をできるようになれば、再び財産管理権を行使するすることが望ましいと考えている。」旨の説明を受けていましたので、当協会は、Yさんに財産管理の事務処理を覚えてもらうため、Wさんの医療費等の立替え払いを依頼し、後日、当該立替金の請求を当協会にしてもらうなど、財産管理書類を定期的に確認してもらう作業を繰り返し行ってもらいました。そして、3年が経過した頃、当協会は、財産管理の引継ぎについてYさんに打診したところ、Yさんは、財産管理を引き受ける意向を示しました。
当協会は、Yさんが保佐人として身上保護と財産管理を行うことがWさんの支援と利益になると考えて、家庭裁判所に保佐人の辞任許可申立てを行ったところ、辞任許可及び複数の保佐人の権限行使の定めの取消しがされました。
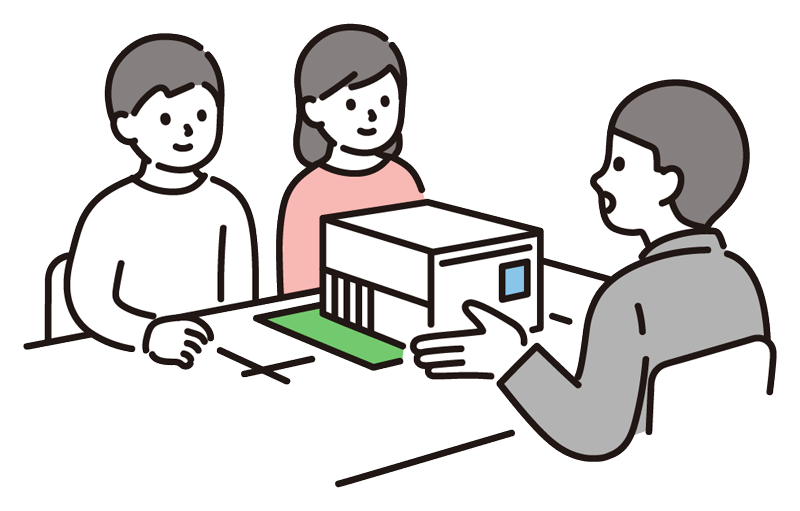
Eさん(被保佐人)は、軽度な知的障害があり、就業はしているものの、食事の用意や金銭管理に関して支援が必要であり、契約など難しい判断には援助が必要でしたので、Eさんが住宅購入及び住宅ローン契約を締結する予定となったことを契機に、母Fさんは、Eさんに対する保佐開始の申立てを行いました。保佐人には、法律実務に詳しい当協会が選任されました。
当協会は、Eさん親子が購入を希望している不動産物件について、Eさんの給与収入及び障害年金からの月々の住宅ローン返済額に無理がないか否か、当該不動産物件から、Eさんの職場への通勤時間に無理はないか否か等を検討し、本件不動産物件購入に同意しました。その後、Eさんは住宅ローンを滞りなく返済しています。
当協会は、当初の課題(住宅購入及びローン契約)が解決したこと、Eさんの生活に必要な支出のほとんどを預金口座からの引落しに変えたことにより、預貯金の管理が容易になったことなどから、母Fさんに財産管理業務を引き継ぎ、保佐人を辞任することを検討することにしました。
そこで、母FさんやEさん本人の意見を聞いた上で、家庭裁判所に保佐人辞任の許可及び代理権付与の取消しの申立て並びに母Fさんを保佐人とする保佐人の選任の申立てを行いました。
後日、申立てどおり、母Fさんが保佐人に選任され、保佐人業務の引継ぎを無事に終えて円滑なバトンタッチを実現しました。
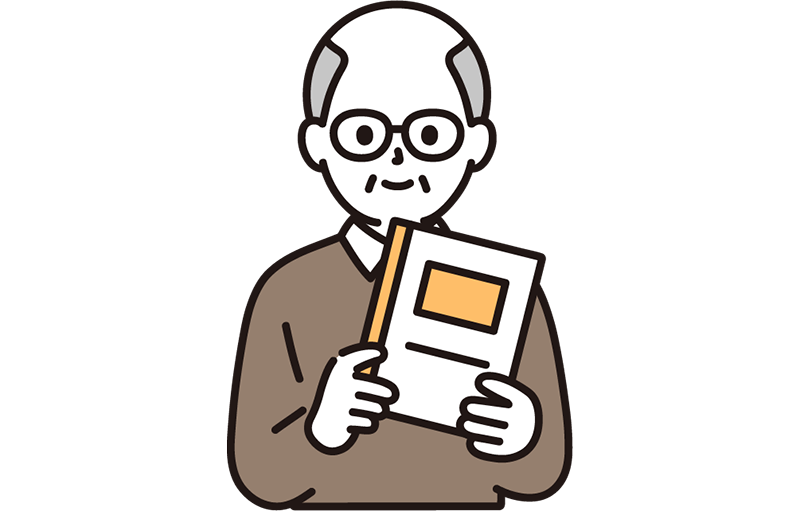
被保佐人であるIさんは、約10年前に金融機関を遺言執行者とする遺言公正証書を作成していましたが、ある日、信頼できる知人に葬儀等を行ってもらうことを条件とする負担付きの遺贈を行いたいと話してくれました。そこで、Iさんの希望を遺言執行者に指定されている金融機関に伝えたところ、条件付きの遺言とするのであれば、このまま遺言執行者を引き受けることはできないとのことでした。
そこで、Iさんの希望を実現するため、作成していた公正証書遺言を撤回し、新たに遺言を作成して新たな遺言執行者を決めることとしました。
被保佐人が遺言をする場合には、保佐人の同意は必要ありません。Iさんは、高齢ではありますが、遺言の内容や効力等について、しっかり理解しています。
Iさんの推定相続人は、本人と面識のない方ばかりなので、Iさんの死後に遺言の効力をめぐって紛争が生ずるおそれがありました。
そこで、公証人と打ち合わせ、Iさんは、遺言をするに足りる判断能力を有している旨の診断書を医師に作成してもらい、公証役場に提出することとしました。遺言執行者については、Iさんの保佐監督人である司法書士が引き受けてくれました。
遺言作成の当日、Iさんは、入所施設を訪れた公証人の前で緊張気味でしたが、本人確認、遺言の内容確認の問いかけにも臆することなく応答したことから、スムーズに新しい遺言が作成されました。
心配事が減り、すっきりした様子のIさんは、入所施設のイベントにも積極的に参加して、元気に過ごしています。
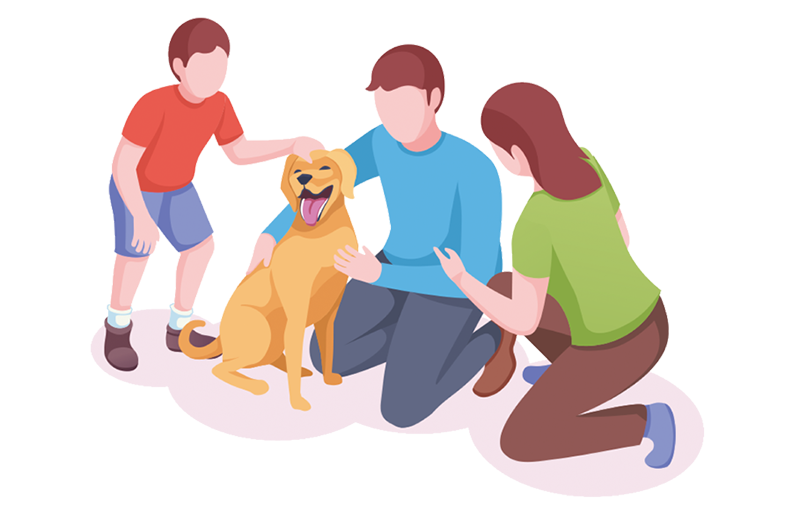
Tさん(被保佐人)は、10年前に飼い始めたM(柴犬)と自宅で暮らしていましたが、Tさんの身体に疾患が見つかり、入院して手術を受けました。手術後のTさんは、身体機能の一部が回復しなかったことから、施設に入所することになりました。
保佐人は、Tさんが入院した翌日から、Mを動物病院に預けましたが、Tさんが自宅に戻ることなく、施設に入所したため、動物病院の利用を続けることとしました。ほかにもペットを預かってくれる施設はありますが、入所金等が高く、Tさんの資力では制約がありました。
そこで、Mを大事にしてくれる人(里親)に譲ることがTさんにとっても、Mにとっても最善と考え、Tさんに提案したところ、Tさんは、Mの里親探しに理解を示してくれました。
里親探しの方法が分からず、数か月が経過した頃、TさんやMの状況を聞いたTさん自宅の近所のYさんから、里親探しへの協力の申し出がありました。里親を募集するポスターを作成して、近隣に掲出するので一切を任せてほしいというものでした。保佐人は、Yさんのご好意に甘えることとしましたが、Mが老犬のためか成果はありませんでした。
気落ちしていたところ、再びYさんから提案があり、里親探しのサイトを利用したらどうかというものでしたので、Yさんに登録をお願いしました。登録してすぐに、Bさんから連絡があり、Mと接したBさんは、Mの健康状態や性格を理解し、トライアルを希望しました。Bさんは、保護犬を引き取って世話をした経験がある方だったので、Mを大事にしてくれると思われました。
1週間後、Bさんから、Mを引き取りたいと申し出がありましたので、譲ることにしました。
後日、BさんからMの写真が送られてきたところ、写真のMは、Bさん家族に囲まれて一家の主のような顔をしていました。

Kさん(被後見人)は、クレジットカードを所持しており、過去に英会話の教材をカードローンで購入したことがありました。そのため、同居の家族からクレジットカードの解約を迫られていました。
Kさんは、「お母さんたちは、クレジットカードを解約しろって言うけど、いざというときがあるかもしれないじゃないか。その時にカードがないと不安なんだよ。」と言って、クレジットカードの解約を拒否し続けていました。
後見人がクレジットカード会社に連絡して過去の利用履歴を確認すると、Kさんは、3年以上カードを使用していないことが判明しました。また、Kさんの月々の収支は黒字であり、クレジットカードの使用だけでなく、支出も自制できていることから、後見人は、Kさんがクレジットカードを保持していても問題がないと判断しました。
Kさんの家族に対し、その旨を説明し、さらに、もしKさんが無計画にクレジットカードを使用するようなことがあれば、後見人が解約できることを説明すると、家族はKさんがクレジットカードを保持することを納得しました。
自分の主張が認められたKさんは、満足した様子でした。
後日、Kさんから、「いろいろ考えたんだけど、クレジットカードを持っていても全然使う機会がないんだよね。今後も使わなそうだから解約して!」と、あっけらかんとした様子で連絡がありました。その後、幾度もKさんに確認しましたが、解約の意思は変わらなかったので、Kさんの希望どおりクレジットカードを解約しました。

Tさん(被保佐人)が入所している施設の職員から、「Tさんは、日中は穏やかに過ごしているが、夜になると荷物を詰め込んだ鞄を持って施設内を徘徊している。その都度、居室に誘導して入眠を促して対処している。」旨の報告がありました。従前はなかった帰宅願望が出ているようでしたが、その原因は判然としませんでした。
保佐人がTさんが入所している施設を訪問して世間話をしながら何気なく心配事はないかと聞いたところ、Tさんは、「ここの人たちは良い人ばかりですよ。」と言って、特に不満は口にしませんでした。しかし、世間話を続けていると、不意にTさんが「ここの支払いってどうなっているのかな。」とつぶやきました。
保佐人は、この発言から、Tさんは、自分が入所している施設の費用等の支払いが不明なことにストレスを感じ、帰宅願望へとつながっているのではないかと推測しました。
そこで、次の訪問からは、Tさんの預金通帳のコピー、年金通知書及び各種領収書等を持参して収支等を説明し、Tさんの疑問を解消することに努めました。
説明を聞いたTさんは、「支払いとかよくわからないから、あなたに任せるわ。でも、あなた以外にそのような話をしてくれる人がいないから助かるわ。」と笑顔を見せてくれました。
後日、施設の職員から「Tさんの夜間の徘徊がなくなりました。」と連絡がありましたが、認知症のため短期記憶が低下しているTさんが、保佐人の説明したことを覚えているとは考えづらいことから、なぜ徘徊抑制にまで至ったのか、実際のところは分からないままです。

Hさん(被後見人)が入所していた施設に、姉のMさんが居住していた自治体から、Hさんに宛てたMさんの介護保険料や後期高齢者医療保険料の還付通知書等が送付されてきました。
後見人は、Mさんが死亡し、HさんがMさんの推定相続人となっていることを初めて知りましたが、民法第915条第1項では、相続の承認・放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないとされています。
後見人としては、HさんがMさんの遺産を相続するか否かを含めて早急に対応を検討する必要に迫られました。
まず、後見人は、Mさんが死亡した事実や連絡先等を調査するため、Mさんの戸籍等を取り寄せました。そして、昔、HさんがMさんから聞いていたMさん宅の電話番号に電話を掛けてみましたがつながりませんでした。
そこで、後見人は、Mさんの居住地であった自治体の高齢福祉課にMさんの生前とその後のことが分かる人の有無を照会してみました。その結果、Mさんが生前に入所していた介護施設が判明したことから、生前のMさんをお世話していたKさんと連絡を取ることができました。
その後、関係者を通じて、Mさんが公正証書による遺言を作成していることが判明しました。遺言の内容は、Kさんを包括的受遺者とし、不動産を含む全財産を遺贈するというものでしたが、可能性としては、Kさんが遺贈を放棄することも考えられました。
Hさんは、遠方に居住しているため、不動産を相続したとしても管理することはできませんし、相続財産の詳細は分かりませんが、Kさんが遺贈を放棄する場合として債務超過であることも考えられますので、後見人は、相続放棄の手続を取ることにしました。
後見人は、Hさんの後見開始の審判をした家庭裁判所の承認を得た後、Mさんの住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しました。そして、同裁判所から、相続放棄申述受理通知書の送付を受けた後、Mさんが居住していた自治体に、Hさんが相続放棄した旨の連絡を行って、本件を終了させました。